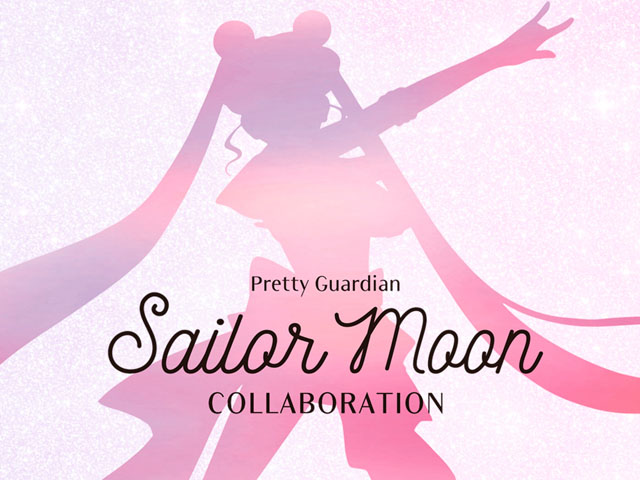厚生労働省が定める放課後等デイサービスの決まり
「放課後等デイサービス」がどのような施設で、どのような子供たちが通うのかは、前記事の「最近良く耳にする放課後等デイサービスとは?」を参考にして下さい。この記事では「放課後等デイサービス」がどういったサービスや活動を提供しているのかを紹介します。
その前提として放課後等デイサービスは「厚生労働省」が作成した「放課後等デイサービスガイドライン」という基準があり、そのガイドラインに沿ってサービス・活動を行う必要があります。このガイドラインに明記されている内容を紹介していきます。

放課後等デイサービスのサービス・活動提供内容
放課後等デイサービスは「厚生労働省」が作成した「放課後等デイサービスガイドライン」という基準があり、そのガイドラインに沿ってサービス・活動を行う必要があります。ガイドラインで定められている活動、サービスは以下の通りです
1.子供の自立支援と日常生活充実のための活動
子供の発達に応じて必要となる日常生活における動作や自立生活を支援するための活動を行う。子供が意欲的に関われるような遊びを通して成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。状況に応じて子供がかよう学校と連携を図りながら行う。
2.創作活動
創作活動では子供たちが表現する喜びを体験できるようにする。またなるべく自然に触れる回数を多くすることで、四季の変化を感じ、各々の感受性を豊かにしていく。
3.地域交流の機会の提供
障害があることで子供たちの社会生活や経験の範囲が制限されないように、子供たちの社会経験の幅を広げていく。日頃から地域交流の場を積極的に設け、様々な体験学習や交流・ボランティア活動などを積極的に行っていくことで地域との交流を図る事。
4.余暇の提供
子供が望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習などの諸活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくために、ゆったりとした雰囲気の中で活動を行えるようにする
※厚生労働省発行「放課後等デイサービスガイドライン」から抜粋
このように、放課後等デイサービスのサービス・活動提供内容は最低限「放課後等デイサービスガイドライン」を満たさないといけないのです。

教室独自のサービス・活動提供
子供の年齢、家族環境、地域環境、教室のタイプなどに応じて、必要となる活動内容が異なってくる事情もある為に、「放課後等デイサービスガイドライン」で定められている主なサービス・活動とは別に各教室がオリジナルの活動を行っているケースも増えてきています。
最近の傾向でいえば、社会に出たときにIT環境を使えるために、パソコンやタブレットに触れておくことで社会生活に適応出来る活動も人気があります。周りのみんなと協力して何かを達成するという体験や経験を積ませるために、家庭菜園や外部施設での体験学習などの機会を増やす教室も増えてきております。
なので、放課後等デイサービスといっても教室によって体験できる活動やサービス内容は大きく変わってきますので、教室選定の際は熟考して子供に何が合いそうかをじっくり検討する必要があります。一体どのような教室があるのかは、次記事の「どんな放課後等デイサービスの施設があるの?」で、説明したいと思います。
*本記事は2018年12月~2019年7月の文献、公式サイト情報などにより記述されております。より正確な最新情報は以下の厚生労働省のサイトでご確認下さい。
障害児支援施策|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
(リンク確認:2019年8月5日)